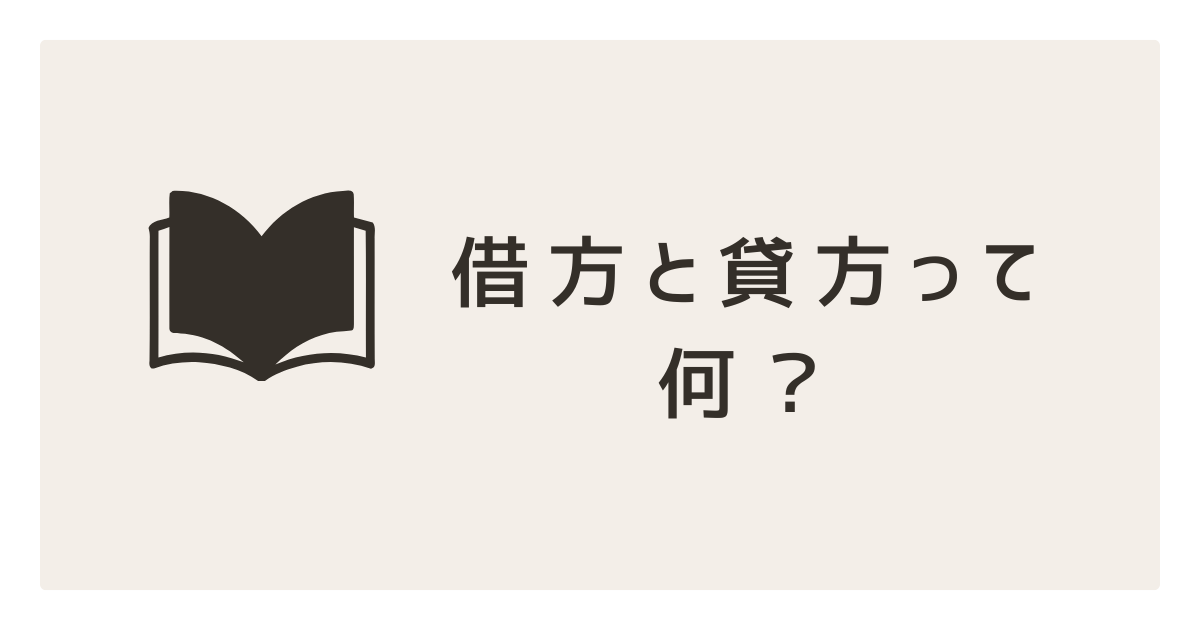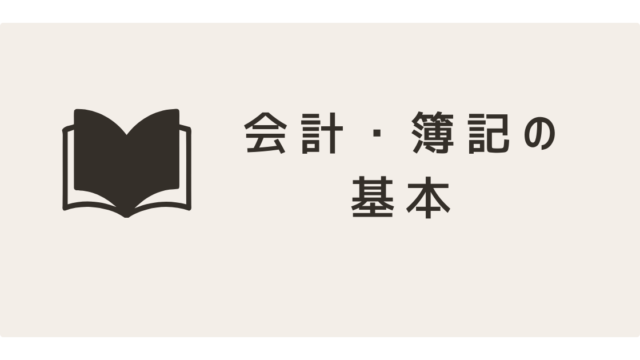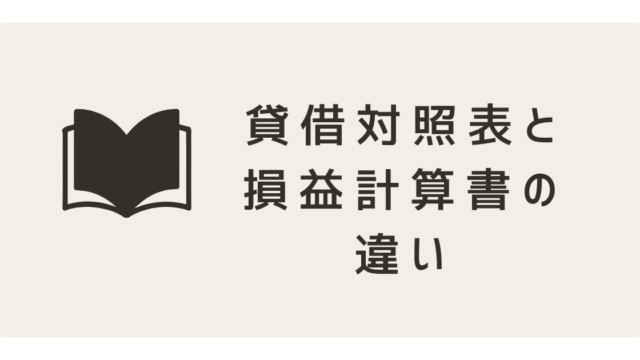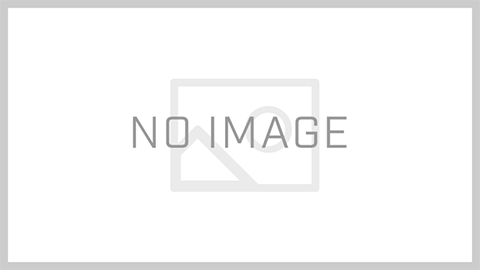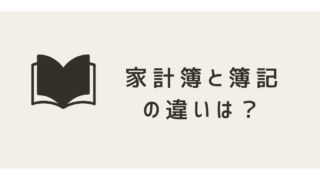「借方(かりかた)」「貸方(かしかた)」という言葉を見ただけで、「なんだか難しそう…」と感じたことはありませんか?
会計の学習を始めたばかりの多くの人が、最初につまずくポイントがこの「借方・貸方」です。読み方はわかるけれど、意味がイメージできない。どっちが左で、どっちが右?そもそも“借りる・貸す”の話じゃないの?──そんなモヤモヤを感じた方も多いのではないでしょうか。
でも安心してください。
実は、借方・貸方の正体は“帳簿の左右の名前”にすぎません。
この記事では、初心者の方にもわかりやすいように、
借方・貸方の意味
どうして会計で使われるのか
どう覚えればいいのか
を、図解や例を使ってやさしく解説していきます。
会計が初めての方でも、「なるほど、そういうことだったのか!」と思ってもらえるような内容になっていますので、ぜひ気軽に読み進めてみてください。
そもそも「借方」と「貸方」ってどういう意味?
「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」は、会計を学ぶうえで必ず登場する言葉ですが、読み方からしてややこしく、初心者の多くが混乱する用語のひとつです。
しかし、ここで大事なのは——
これは“借りる・貸す”の意味ではないということです!
「借方=左」「貸方=右」という“場所の名前”
会計では「仕訳(しわけ)」という方法で、すべての取引を帳簿に記録します。
この仕訳はT字型の帳簿に記入され、「左側」と「右側」にそれぞれの情報を書き分けるルールがあります。
このときに使われる左右の名称が、
左側:借方(Debit)
右側:貸方(Credit)
つまり、「借方・貸方」とは“帳簿の左と右のことを指す名称”にすぎません。
借りる・貸すの意味ではない!
「借方」と聞くと「誰かからお金を借りること?」と思いがちですが、会計上の借方にはそういった意味合いはありません。
仕訳のルール上、たとえば「現金が増えた」などの取引は借方(左側)に記録される、というだけの話なのです。
ポイントは「左右で何が増えるか」
借方・貸方の本質を理解するには、「どの項目がどちらで増えるのか」を押さえておくのが近道です。
借方(左)で増えるもの:資産、費用
貸方(右)で増えるもの:負債、資本、収益
このように、「左右どちらに何を書くか」は会計のルールとして決まっているので、それに従って仕訳を行います。
まとめ
借方と貸方は、取引を帳簿に正確に記録するための“左右のラベル”です。
「借りた」「貸した」と混同せず、「これは左」「これは右」と位置で覚えることが、理解への第一歩になります。
次は、図を使ってこの左右の関係をもっと具体的に見ていきましょう!
借方と貸方の関係性を理解しよう
借方(左)と貸方(右)の考え方をしっかり理解するためには、そのルールをおさえましょう。
■ 「増えたらどっち?」がわかればOK!
帳簿に記録する時のルールは以下の通りです。
| 勘定の種類 | 増えた時に記録する側 |
|---|---|
| 資産(現金、建物など) | 借方(左) |
| 費用(仕入れ、給与など) | 借方(左) |
| 負債(借入金など) | 貸方(右) |
| 資本(資本金など) | 貸方(右) |
| 収益(売上など) | 貸方(右) |
これを覚えておくと、「現金が増えたから借方」「売上があったから貸方」といった仕訳の判断がスムーズになります。
■ 仕訳の基本=左右にバランスよく書くこと
取引を記録する際は、必ず借方と貸方の両方に金額を記入し、左右の合計が一致するようにします。
これを「仕訳」といい、会計の基本動作です。
たとえば:
「文房具を1,000円で買って、現金で支払った」場合の仕訳はこうなります。
借方(左):消耗品費 1,000円(費用の増加)
貸方(右):現金 1,000円(資産の減少)
まとめ
「借方=左、貸方=右」がどんなルールで使われるのかを理解しておくことが、仕訳や簿記の理解につながっていきます。
次は、「どの項目がどちらに書かれるか」を一覧で見られる早見表をご紹介します!
覚えやすい!借方・貸方のルール早見表
会計の基本ルールである「借方」と「貸方」をしっかり覚えるためには、どの勘定科目がどちらに記録されるのかを一覧で見ることが大切です。
この早見表を使えば、仕訳の際に迷うことが少なくなりますよ!
借方(左)に記録するもの
資産が増えるとき(現金や土地、備品など)
→ 例:現金 10,000円増えた費用が増えるとき(仕入れや人件費など)
→ 例:広告費 5,000円負債が減るとき(借入金など)
→ 例:借金 2,000円返済
貸方(右)に記録するもの
資産が減るとき(現金や在庫など)
→ 例:現金 3,000円減った収益が増えるとき(売上や利益など)
→ 例:売上 15,000円負債が増えるとき(借入金など)
→ 例:借入金 5,000円増えた資本が増えるとき(資本金など)
→ 例:株主資本 10,000円増加
覚え方のコツ
借方(左)=資産・費用の増加
貸方(右)=収益・負債・資本の増加
この基本ルールを覚えておけば、あらゆる取引で「どちらに記録するべきか」を瞬時に判断できるようになります。
まとめ
この早見表を参考にして、借方・貸方の記録方法をしっかり覚えましょう。
仕訳のルールを守ることで、より正確な帳簿管理ができ、会計の基礎力を高めることができます。
次は、実際の仕訳例を見てみましょう。具体的な取引を通して、どのように借方と貸方を記入するのかを理解していきます。
仕訳の例でイメージしてみよう
借方・貸方のルールがわかってきたら、次は実際の取引がどう仕訳されるのかを見てみましょう。
仕訳とは、取引を「借方(左)」「貸方(右)」に分けて帳簿に記録すること。ここでは、日常的によくあるシンプルな仕訳の例を使って、感覚をつかんでみましょう。
例①:文房具を現金で1,000円購入した
借方(左):消耗品費 1,000円(費用が増加)
貸方(右):現金 1,000円(資産が減少)
ポイント:モノを買って費用が増えた → 借方、現金が出ていった → 貸方
例②:お客様に5,000円の商品を売って、現金を受け取った
借方(左):現金 5,000円(資産が増加)
貸方(右):売上 5,000円(収益が増加)
ポイント:現金が増えた → 借方、売上が立った → 貸方
例③:給料を銀行振込で支払った(10,000円)
借方(左):給与手当 10,000円(費用が増加)
貸方(右):普通預金 10,000円(資産が減少)
ポイント:給料という費用が発生 → 借方、預金が減った → 貸方
例④:銀行から20,000円を借り入れた(現金受取)
借方(左):現金 20,000円(資産が増加)
貸方(右):借入金 20,000円(負債が増加)
ポイント:お金が入ってきた → 借方、借金が増えた → 貸方
まとめ
仕訳は「何が増えた or 減ったのか」を見て、借方と貸方に分けて記録するだけ。
慣れないうちは混乱しがちですが、実際の取引で何が起きたのかを想像しながら書くと、自然と身についていきます。
次は、初心者がつまずかないための「覚え方のコツ」をご紹介します!
「借方・貸方」に迷わないコツと覚え方
「借方って左?右?」「売上はどっちに書くの?」
簿記や会計の学習で、最初にぶつかる“あるあるの壁”が「借方・貸方の迷い」です。
でも大丈夫。覚え方のコツをつかめば、スムーズに理解できるようになります!
■ まずは「左右の意味」をしっかり覚える
借方(かりかた)=左側(Debit)
貸方(かしかた)=右側(Credit)
これは絶対に変わらないルールです。帳簿の形式(T勘定)を思い浮かべると、視覚的に記憶しやすくなります。
ポイント:
借方・貸方は“動き”ではなく“位置の呼び名”と割り切って覚える!
■ 「増えるのはどっち?」をイメージで暗記!
| 増えると借方(左)に書く | 増えると貸方(右)に書く |
|---|---|
| 資産(現金・土地など) | 負債(借金など) |
| 費用(仕入・給料など) | 資本(出資金など) |
| 収益(売上など) |
この表を覚えると、実際の仕訳で「どっちに書けばいいか」の迷いが一気に減ります。
■ ゴロ合わせで楽しく覚える方法も
「ヒサヒサカシシュ」(資産・費用=左、負債・資本・収益=右)など、語呂で覚える人も多いです。
ヒ(資費)サ(資産)=借方(左)
カ(貸)シ(資本)シュ(収益)=貸方(右)
自分に合った覚えやすい言葉をつくるのもおすすめです。
■ 実際に“仕訳をたくさん書く”のが一番の近道!
仕訳はスポーツや楽器と同じ。繰り返すことで自然と体にしみ込んでいきます。
練習問題を毎日1問だけでも解いてみる
自分の身の回りの取引を仕訳にしてみる
(例:ランチ代 → 借方:食費/貸方:現金)
「正確さより慣れること」を意識して、気軽に取り組みましょう。
まとめ
借方・貸方の理解に迷ったら、
左右のルールに立ち返る
増減パターンを表で覚える
実際に手を動かして定着させる
この3ステップを意識するだけで、仕訳の理解が一気に深まります。
次回からはもう、借方と貸方で迷わないはずです!
まとめ|借方・貸方は“会計の土台”になる考え方!
ここまで、「借方」と「貸方」の意味や使い方、覚え方についてやさしく解説してきました。
最初は戸惑いやすい言葉ですが、その正体はとてもシンプル。「帳簿の左右に何を記録するか」という、会計の基本ルールにすぎません。
✔ 借方(左)=資産・費用が増える
✔ 貸方(右)=負債・資本・収益が増える
このルールを押さえれば、会計の“見えない地図”がグッとわかりやすくなります。
仕訳や帳簿づけなど、これから先に出てくるすべての会計処理は、この「借方・貸方」の考え方をもとに成り立っています。
つまり、今日学んだこの内容こそが、会計の“土台”なのです。
最後にひとこと
最初は覚えるのが大変でも、少しずつ仕訳の練習を重ねていくうちに、自然と手が動くようになります。
焦らず、自分のペースで学びながら、会計の世界に一歩ずつ慣れていきましょう。
あなたの「なんとなく不安だった会計」が、「なんとなくわかるかも」に変わったなら、もうそれは立派な第一歩です!