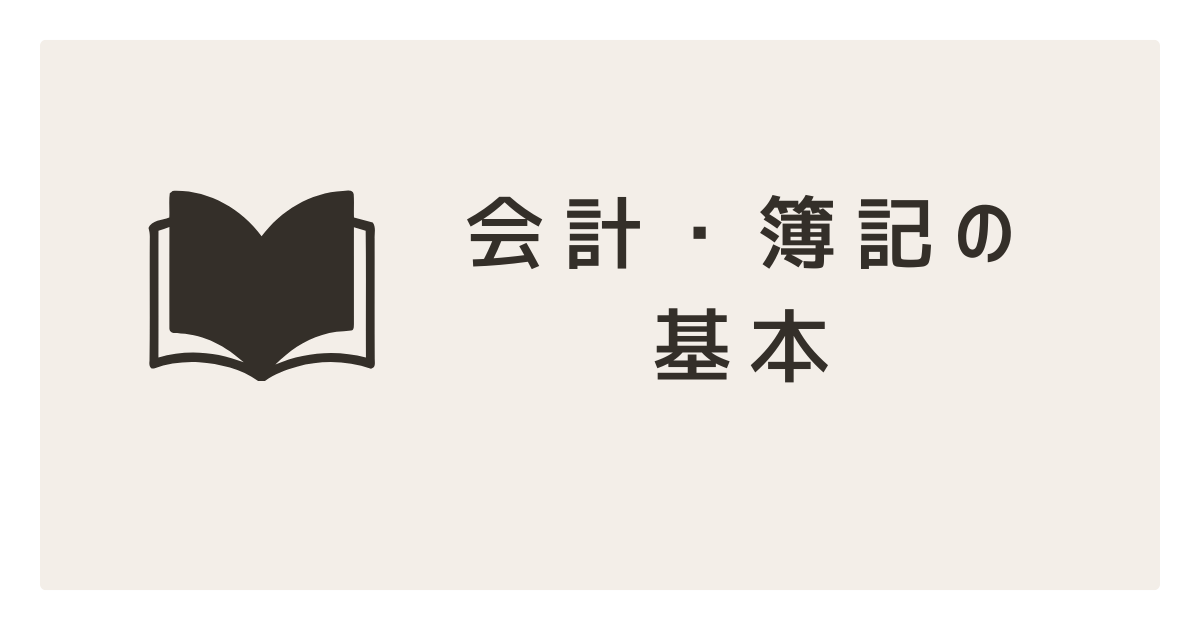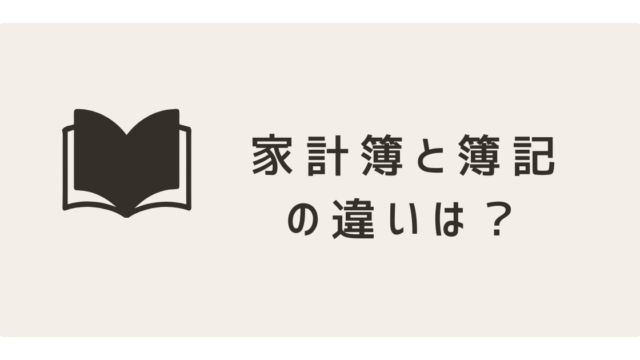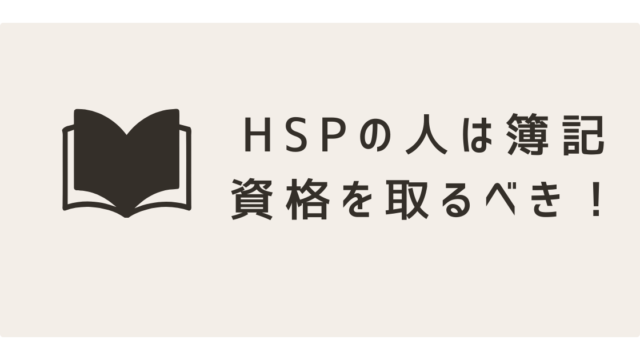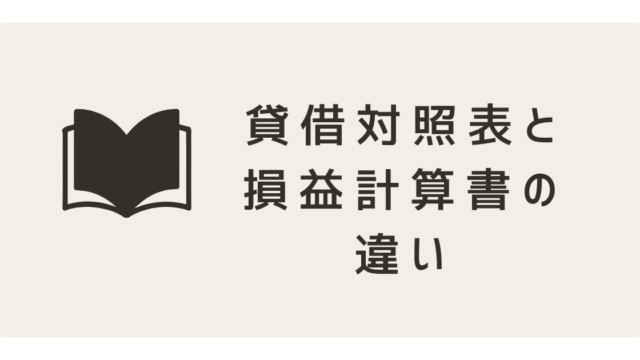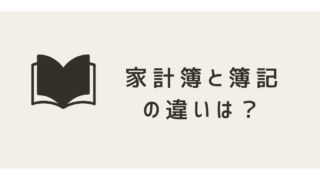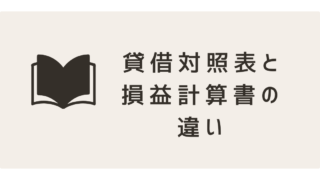「会計」と聞くと、難しそうな数字や専門的な知識をイメージするかもしれません。しかし、実は会計とはとてもシンプルな考え方で、「お金の流れを記録し、整理し、報告すること」を指します。
たとえば、あなたが毎月家計簿をつけているとしましょう。収入はいくらか、支出に何を使ったか、今どれくらいの貯金があるかを把握するために記録しているはずです。これこそ、まさに“会計”です。
会計は、主に以下の3つのステップで成り立っています。
記録(取引を記帳する)
例:売上があった、経費を支払ったなどの事実を帳簿に記録する。整理(分類・集計する)
記録した情報を「売上」「仕入」「経費」などに分類し、集計してわかりやすくする。報告(外部や内部に伝える)
決算書などの形で、会社の経営状態やお金の流れを「見える化」して伝える。
| 家計簿の場合(個人) | 会計の場合(企業) |
|---|---|
| 記録 お給料や支出をメモ | 記録 売上・経費などを帳簿に記録 |
| 整理 食費、光熱費などカテゴリ別にまとめる | 整理 勘定科目ごとに分類・集計 |
| 報告 毎月の家計簿や予算表で見える化 | 報告 財務諸表(B/S、P/L)を作成・提出 |
このように、個人で行う「家計簿」も、企業が行う「会計」も本質は同じ。
どちらも「今いくらあるのか」「どれくらい使ったのか」を把握して、将来の意思決定に役立てるためのツールです。会計とは「お金の動きを見える形にすること」であり、企業だけでなく、個人にも役立つとても身近なスキルです。
会計の目的と役割
会計には「なぜやるのか?」「何のために必要なのか?」という明確な目的があります。単に数字を記録するだけでなく、その情報をもとに「正しく判断し、よりよく行動する」ための土台をつくるのが会計の役割です。
主な目的と役割は、以下の3つです。
1. お金の流れを“見える化”して管理する
企業でも個人でも、収入や支出を把握していなければ、どれだけお金が残っているか、何に使いすぎているかがわかりません。
会計は、こうした「お金の使い道」を整理して、収支や残高を見える形にすることで、効率的な資金管理を可能にします。
2. 経営判断の材料を提供する
「この商品は利益が出ているのか?」「新しい設備投資をする余裕はあるのか?」など、ビジネスには日々の意思決定が欠かせません。
会計データをもとに分析を行えば、感覚ではなく“数字に基づく判断”ができるようになり、経営のリスクも減らせます。
3. 社外に情報を正しく伝える
会計は社内だけでなく、株主や銀行、税務署といった“外部の人たち”にも会社の状況を伝える重要な役割を持っています。
たとえば、財務諸表(決算書)を見れば「この会社は利益を出しているか」「借金は多いか」などが一目でわかります。
まとめ
会計は「お金をただ記録するだけ」のものではありません。
お金の流れを整理し、意思決定に活かし、社内外の信頼を築く――そのすべてを支えているのが会計なのです。
会計の基本用語をやさしく解説
会計の世界では、専門的な用語がたくさん出てきますが、実は基本となるのはたった「3つの表(財務諸表)」です。
それぞれの役割をざっくりつかむだけでも、会計の全体像が見えてきます。
1. 貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう / Balance Sheet:B/S)
会社の“持ち物”と“借り物”を表す表。
簡単にいうと、会社がどんな資産を持ち、どこからお金を集めているかを表したものです。
資産:現金、建物、在庫など「持っているもの」
負債:借金、未払い金など「返すべきもの」
純資産:資産から負債を引いた「会社の本当の価値」
たとえば:
「現金が100万円あるけど、借金が80万円あるから、純資産は20万円」というイメージです。
2. 損益計算書(そんえきけいさんしょ / Profit & Loss Statement:P/L)
会社の“もうけ”や“赤字”を表す表。
一定期間(例えば1年間)に、どれだけ売上があって、どれだけ費用がかかったか。その結果「利益が出たのか」「損をしたのか」を見るための表です。
売上:商品の販売やサービスで得たお金
費用:仕入れや人件費など
利益:売上 − 費用
たとえば:
「100万円売れて、70万円かかったから、利益は30万円」という感じです。
3. キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement:C/F)
実際に“お金が入った・出た”流れを表す表。
「利益が出ているのにお金がない」ということもあるため、現金の動きをチェックするために使います。
営業活動によるキャッシュフロー(本業の入出金)
投資活動によるキャッシュフロー(設備投資など)
財務活動によるキャッシュフロー(借入・返済など)
たとえば:
「商品は売れてるけど、まだ代金が振り込まれていない=利益はあるけど現金はゼロ」というケースもあるんです。
まとめ
この3つの表(B/S、P/L、C/F)を理解すれば、会計の“地図”が頭の中にできます。すべての会計データはこの3つのどれかに関係しています。
最初は細かく覚えなくてもOK!
まずは「何のための表なのか」をイメージできれば、会計の苦手意識はグッと減りますよ。
これだけは知っておきたい!「借方」と「貸方」
会計の世界に足を踏み入れると、必ず出てくるのが「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」という用語。
この言葉を見ただけで「もう無理かも…」と思った方、ご安心ください!
実は、「借りた」「貸した」ではないんです。
■ 借方・貸方は“左右の位置”の名前
帳簿(仕訳帳)では、1つの取引を2つに分けて記録します。これを「複式簿記」といいます。
借方(左側)
貸方(右側)
つまり、「借りた」「貸した」という意味ではなく、“どっち側に書くか”のルールなんです。
■ 覚え方のコツ:増えるとき、減るとき
どちらに書くかは、「何の項目が増えた or 減ったか」で決まります。以下のようなルールを覚えておくと便利です。
| 勘定科目 | 増えたとき | 減ったとき |
|---|---|---|
| 資産(現金・建物など) | 借方(左) | 貸方(右) |
| 負債(借入金など) | 貸方(右) | 借方(左) |
| 資本(自己資本など) | 貸方(右) | 借方(左) |
| 収益(売上など) | 貸方(右) | 借方(左) |
| 費用(仕入・給与など) | 借方(左) | 貸方(右) |
■ 身近な例でイメージしよう
たとえば「商品を現金で1,000円分買った」という取引の場合…
借方(左):仕入 1,000円 → 費用が増えた
貸方(右):現金 1,000円 → 資産(現金)が減った
「仕入が増えたから借方」「現金が減ったから貸方」に書く、というわけです。
まとめ
借方と貸方は、「どちらに何を書くか」という“会計のルール”です。
「借りた・貸した」と混同しないことが大事!
最初は混乱しても、何度も実例に触れるうちに自然と慣れてきます。
日常生活で使える会計的な考え方
会計と聞くと「企業や経理の専門知識」と思われがちですが、実は会計の考え方は、私たちの日常生活にもそのまま応用できます。
お金の使い方を見直したり、将来のために計画を立てたりするのに、とても役立つのです。
1. お金の「流れ」を意識する
多くの人が「貯金が増えない」「気づいたら使っている」と感じるのは、お金の動きを正確に把握していないから。
会計では「入ってきたお金(収入)」と「出ていったお金(支出)」を記録して、差額を見ます。これは家計にもそのまま使えます。
たとえば:
「1か月の手取り25万円」「家賃8万円」「食費4万円」…という風に書き出せば、何に使いすぎているかが見えてきます。
2. 「資産」と「負債」を分けて考える
会計では「資産(持っているもの)」と「負債(返すべきもの)」を分けて管理します。
この考え方を使えば、“本当の意味での貯金”がいくらあるのかが見えてきます。
たとえば:
現金が50万円あっても、クレジットカードの未払いが30万円あれば、「純資産」は20万円です。
3. 将来の意思決定に役立つ
会計の目的のひとつは、数字をもとに「今後どうするか」を判断すること。
これも生活に応用できます。
たとえば:
「今年中に旅行に行きたいから、毎月1万円ずつ積立てよう」
「引っ越し資金として家賃を見直すべきかも」
こうした行動は、会計的な“予算と計画”の発想です。
まとめ
会計とは「お金の流れを見える化して、未来のために考える力」。
企業だけでなく、私たち個人の生活にも役立つスキルです。
家計簿をつけるのも立派な会計の第一歩。日常に少しだけ“会計の視点”を取り入れてみませんか?
初心者におすすめの学習方法・ステップ
「会計を学びたいけれど、何から始めたらいいかわからない」
そんな方に向けて、会計初心者がスムーズに知識を身につけられる学習ステップをご紹介します。
難しく考える必要はありません。大切なのは“順序よく学ぶこと”です。
ステップ1:まずは全体像をざっくり理解しよう
いきなり仕訳や帳簿に入るのではなく、まずは「会計って何をするものなのか?」という全体像をつかむことが大切です。
おすすめ:
「会計とは?」の入門記事や動画を見る
家計簿と企業会計の共通点をイメージする
ステップ2:基本用語と財務3表を覚える
会計の基本は「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」「キャッシュフロー計算書(C/F)」の3つ。
難しそうに見えて、実はそれぞれ役割が違うだけ。図解や事例で見ると一気に理解が進みます。
おすすめ:
会計入門書で3つの表の意味を学ぶ
YouTubeなどで図解付きの動画を見る
ステップ3:仕訳のルールを身につける
会計の「基礎体力」となるのが仕訳(しわけ)です。借方・貸方に分けて記録する方法を覚えることで、実践的な力がつきます。
おすすめ:
簿記3級のテキストで基礎を練習
簡単な取引の仕訳例を繰り返す
ステップ4:実際に手を動かして練習する
会計は、“見てわかる”より“やって覚える”のが効果的。
模擬問題やワークブックを使って、自分で帳簿を書いてみましょう。
おすすめ:
市販の問題集や無料アプリで仕訳練習
小さな架空の会社を想定して帳簿をつけてみる
ステップ5:簿記検定にチャレンジしてみる
ある程度理解が進んだら、日商簿記3級などの検定試験に挑戦するのもおすすめです。
体系的に学べるだけでなく、「目標」があるとモチベーションも続きやすくなります。
おすすめ:
簿記3級は独学でも合格可能!
通信講座や無料のYouTube講座も活用しよう
まとめ
会計は一見むずかしく見えますが、正しい順番で学べば、誰でも理解できます。
「数字が苦手」でも、最初はイメージをつかむだけでOK。焦らず、自分のペースで学習を進めましょう。
まとめ|会計は“お金の見える化”の力!
ここまで、会計の基本や考え方について見てきました。
最初は「むずかしそう」と感じていた方も、会計が私たちの生活やビジネスに深く関わっていることがわかってきたのではないでしょうか。
会計の本質は、とてもシンプルです。
それは、「お金の流れを見える形にすること」。
今、いくら持っていて
何にどれだけ使っていて
将来どうなるのか
こうした情報を整理し、数字という“事実”をもとに判断や行動ができるようにするのが、会計の力です。
そしてこの力は、企業だけでなく、私たち個人の暮らしにも大いに役立ちます。
家計を見直すとき、将来の目標を立てるとき、節約や投資を考えるとき——
“会計的な視点”があることで、お金との付き合い方が変わります。
最後にひとこと
会計は、特別な人だけのものではありません。
誰でも、今日から少しずつ身につけていける“人生に役立つスキル”です。
まずは家計簿をつけてみる、小さな仕訳に挑戦してみる——
そんな第一歩から、あなたの“お金の見える化”が始まります。